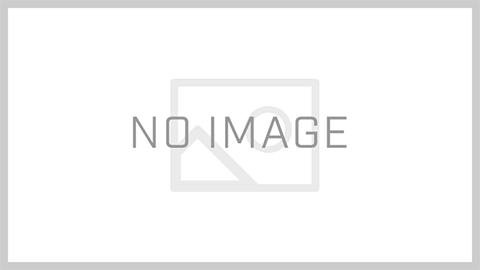「…かれこれもう2時間寝かしつけしている」
「なんで寝ないの?昼寝もしていないじゃん」
「つらい…。なぜこの子はこんなにも寝ないの?」
毎晩のように悩み苦しんでいませんか?
そして「なぜ寝ないのか」理由も分からず、先の見えない状況に不安を感じていませんか?
今回の記事では、お子さんの睡眠問題に悩み続けるママが少しでもラクになるヒントをお伝えいたします。
今年6歳になる発達障害の長男を育てている、さとちえです
長男は生まれた時から寝ない子でした。
同じ部屋に入院する赤ちゃんがぐっすり寝ている中、30分置きに泣く長男。
成長しても1、2時間置きに泣いて起きる日々。
2歳手前でお昼寝をしなくなり、夕方頃には機嫌が悪くずっと泣いている。
なのになぜか夜も寝ない…
当然面倒を見る私も睡眠不足が続き、常にイライラしていました。
挙句、
「なぜこんなに寝ないの?!ママをちょっと寝かせてよ!」
と怒る毎日。
自己嫌悪、だけど眠い。夫は交代してくれない…家事も残っている…
そんな毎日に嫌気がさしていました。
それでもなんとか子どもの睡眠を改善しようと、さまざまな方法を試してみました。
その中で知ったのは、「実は寝かせるための対策よりも大事なことがある」ということ。
今回は、私が経験した「眠れない日々」の話を交えながら、
・なぜ発達障害児は寝ないのか
・私がやってみて効果のあった方法
・お子さんが寝れない夜にママに試して欲しいこと
こちらをお伝えしたいと思います。
「子どもと一緒にぐっすり寝たい」
この思いを叶えるため、ぜひ一つずつ試してみてくださいね。
【なぜ寝ない】発達障害児の睡眠問題の原因3選
ここでは「なぜ発達障害児は寝ない子が多いのか」について、考えられる原因を3つお伝えいたします。
①脳の構造と特性によるもの
②環境刺激を受けすぎている(or刺激が足りていない)
③ママの不安が伝わり、子どもが安心できていない
一つずつ解説いたします💡
①脳の構造と特性によるもの
発達障害を持つ子は一般の子に比べ、脳機能の発達が不十分と言われています。
そのために睡眠障害を始め、睡眠に影響する「感覚過敏」や「過活動」、「ストレス耐性の弱さ」といった発達障害の特性が出現。
そして、これらの特性がどう睡眠に影響するかというと、
| 特性 | 睡眠への影響 |
| 感覚過敏 | ちょっとした物音や光で目が覚めやすい、または眠れない |
| 過活動 | 交感神経が働き続け、常に興奮状態にあるので、副交感神経が働かず眠れない |
| ストレス耐性の弱さ | 日常生活でストレスを感じやすく、そのために眠れないもしくは睡眠が浅く、すぐに起きてしまう |
こういった状態が起きやすいので、発達障害の子は、
「なかなか寝付けない」
「寝たと思ってもすぐ起きる」
といった睡眠障害が生じやすいのです。
②環境刺激を受けすぎているor刺激が足りていない
音、光、気候、ストレスなどの環境刺激を受けすぎていることも睡眠に影響を及ぼします。
発達障害の子は感覚過敏を持ち合わせていることが多く、そのために音や光などの刺激を受けすぎてしまいます。
するとその刺激がいつまでも体に残り、
交感神経を刺激→興奮状態が続く→眠れない
といった現象を引き起こすことに。
例えば、ディズニーランドや遊園地、ライブ観戦などに行った後、興奮状態が続いて眠れない、といった経験をしたことはありませんか?
発達障害の子は、日常的にこういった状態に陥っているのです。
それはなかなか眠れませんよね…
(私も一昨年阪神が日本一になった日の夜は、興奮がなかなか覚めず眠れませんでした🐯)
反対に、日中受ける刺激が少なすぎても寝つきが悪くなる可能性があります。
体に入る刺激量が少ないため疲れにくく、寝る時間になっても元気いっぱい…!
これは発達障害の子に限らず、一般の子でもよく起こりますよね。
雨の日など室内で1日遊んだ日は、お昼寝をしない、夜もなかなか寝ない、といったことが起こりがち。
刺激が少なくても寝ない、刺激が多くても寝ない…
ちょうどいい塩梅というのはなかなか難しいですね😭
③ママの不安が伝わり、子どもが安心できていない
これは毎日一生懸命頑張るママにとっては、耳を塞ぎたくなるお話ですよね…
私も毎日長男の寝かしつけに苦戦し、自分も寝不足でフラフラの中でこの話を聞いた時は、
「どうして私のせいにするの?」
「結局、私が悪いの?」
と、周りから責められたような気持ちに陥っていました。
しかし、「私の不安な気持ちが長男に伝染して、眠れなくなっているのかもしれないな」と、確かに感じることもあったのです。
それは、夫が出張で不在のある土曜日のこと。
「もう今日は長男と寝ちゃおう」
と、夕方からお酒を飲んで2人でテレビを見て過ごしていました。
寝る時間になり2人で布団に入っていたところ、長男が珍しく私の腕にギュッと抱きついてきたのです。
当時2歳半近くの長男。
ようやく出始めたぎこちない言葉で「ママ、ねんね、うれしい」と言ってくれたのです。
その姿が嬉しくて、可愛くて、私も思わず「かわいい〜!好き!」と返答。
そのまましばらく2人でギューギューしていたら、なんといつの間にか長男が寝ていたのです。
わずか30分という長男史上最速の寝かしつけタイムに驚きを隠せない私。
その時に感じたのは、「毎日必死で寝かそうとしている緊張状態が、長男に伝わっていたんだな」ということ。
発達障害の子は、人一倍周りの空気を敏感に感じ取る、と言われています。
大好きなママだからこそ、余計に気持ちを察知してしまうのかもしれませんね。
そうは言っても毎日大変な中、「ママがお子さんに不安を見せない」というのは至難の業なので、
まずは次でご紹介する「コレで長男は寝た|私が試して効果のあった方法」をぜひ試してみてくださいね。
コレで長男は寝た|私が試して効果のあった方法3選
ここからは、私が実際に試してみて効果のあった方法を3つご紹介します。
①睡眠環境を整える
②夕方から刺激を減らす
③寝る前のスキンシップを増やす
順に一つずつご紹介いたします💡
①睡眠環境を整える
一般的に言われている「睡眠環境を整える」ことは、長男にとって一定の効果がありました💡
具体的には、
・遮光カーテンを使用して光刺激を遮断したことで、寝つきが良くなった&途中で起きることがなくなった
・小さくオルゴールをかけ、外部からの音による刺激を減らしたことで、何度も寝かしつけに失敗することが少なくなった
こういった効果が見られるようになりました。
長男は感覚過敏があり、特に音と光に対して敏感に反応。
思えば赤ちゃんの頃から、太陽光やベッドの「ミシッ」という音で起きてしまう子でした。
そんな時に知ったのが、この「刺激をカットする」方法。
遮光カーテンとオルゴールを使用することで、
・寝かしつけ時間が2時間→30分に短縮
・夜泣きの頻度が毎日→1週間に1回に激減
・朝までぐっすり寝る日も多くなった
と、なんとも感動的な結果を生み出すことに成功しました!
なお、音の刺激をカットする方法として我が家はオルゴールを用いていますが、一般的には「ホワイトノイズ」を使用するのがオススメ。
ホワイトノイズ…胎内で聞いていた、ママの血流の音を再現したもの。これを聞くことで安心して眠れるとともに、外部の音を掻き消す効果もあるため、途中で起きるのを減らすことができる
YouTubeでの無料音楽や、商品としても販売されておりますので、ぜひ試してみてくださいね。
ちなみに長男は「この、おと、いや」と拒否され、泣く泣くオルゴールに変更。
(それでもオルゴールで寝つきが良くなりました✨)
むしろ、次男が気に入ってホワイトノイズを使っております!
(旅行先に持って行くのを忘れたら、めちゃくちゃ怒られました…笑)
遮光カーテンやホワイトノイズ、ぜひ試してみてくださいね🌷
②夕方から刺激を減らす
夜の寝つきを少しでも良くするため、夕方から環境刺激を減らすことも効果的💡
我が家の場合は、
・16時過ぎ頃から、リビングの照明を暖色にする
・寝る2時間前にテレビ終了
・38℃前後の湯船に浸かる
これらの対策を行なっています。
目的としてはどれも環境刺激を減らす(光、音)ですが、ポイントは「湯船に浸かる」ということ。
これは、「湯船に入ることで副交感神経が働き、1日受け取り続けた刺激を減らす効果が期待できる」のです!
照明、テレビと合わせて長男に試したところ、確かに寝つきがぐっと早くなりました✨
なんなら、入浴後から目を擦ってウトウトし出すことも…!
ちなみに我が家の長男は大のお風呂嫌いでしたが、こちらも対策を行うことでスムーズに入ってくれるようになりました。
(対策については、近日公開予定の記事で詳しくご紹介します!)
「照明、テレビ、お風呂、この中のどれか一つでも効果はあるの?」
確かに、疑問に思われますよね。
しかも毎日忙しいママ、嫌がるお子さんを無理やりお風呂に入れたり、テレビを消すということはかなり難易度高いですよね…
長男も最初は苦戦し、照明を暖色にすることしかできませんでした。
それでも2時間の寝かしつけが、お気持ち早まったかな?という効果はあったように思います。
しかし、日中に浴びた刺激はできる限り減らした方がいいので、可能ならすべてセットで行うことをオススメします。
長男もすべて行うようになってから、2時間→30分と寝かしつけ時間が格段に短くなりました!
我が家で行ったテレビを消す際の声がけや、お風呂対策についてはまた別な記事でご紹介いたします。
無理のない範囲で取り組んでみてくださいね🌷
③寝る前のスキンシップを増やす
寝かしつけの前にお子さんとのスキンシップを増やすのもとても効果があります。
具体的には、
・お子さんとハグをする
・手をつなぎながら本を読む
・「大好きだよ」と伝える
といった方法ですが、どれも簡単に試せるものです💡
なのに、寝かしつけへの効果はバツグン!
長男は「大好きだよ」と伝え始めた頃から、自分から「おやすみ」と言って寝ることも多くなりました。
しかも30分かからずに寝つくことも◎
この経験から、
「発達障害の子は繊細で敏感な子が多く、不安を感じやすい」
「安心感を与えることでぐっすり眠れるようになる」
ということを身に染みて感じるようになりました。
寝る前のお子さんとのスキンシップ、ぜひ試してみてくださいね🌷
お子さんだけでなく、ママの気持ちも落ち着くことができるかと思います✨
【お子さんが寝ない夜】ママがラクなるために試してみてほしいこと
一生懸命寝かしつけてもお子さんが寝てくれないと、だんだんイライラしてきてしまいますよね。
私は何度も子どもに向かって「なんで寝ないの?!」と怒ってしまったこともあります…
日中子どもに時間を費やしている分、「せめて夜は自分の時間がほしい…!」思っていると、寝かしつけにも力や焦りが入りますよね…
もう、すっごくお気持ち分かります!
なんなら先に夫がぬくぬくしているとさらにイライラが…😇
…と、話が脱線してしまいましたが、「あれこれ対策を試してもお子さんが寝ない!」そんな夜に、ママがラクになるちょっとしたコツについてお伝えいたします。
「あ、これやってみようかな?」と思えるものがありましたら、ぜひ試してみてくださいね✨
①一度リビングで一緒に過ごしてみる
②子どもと一緒に寝ちゃう
一つずつ解説いたします!
①一度リビングで一緒に過ごしてみる
寝かしつけてもお子さんが寝ない時、無理に続けず一度リビングに戻るというのも効果的💡
場所をかえることでお子さん自身も一旦切り替えられますし、何よりママの焦る気持ちを落ち着かせる効果があります。
過ごし方は、ママの気持ちが落ち着く方法ならなんでも◎
我が家は一緒に本を読んだり、子どもを遊ばせながら家事を終わらせる、などして過ごしております。
コツは、予め時間を決めてリビングで過ごすこと💡
我が家は長男に時間を決めてもらったうえで、
「◯時までは好きなことしていいから、時間が来たら寝るよ」
と声がけしてリビング時間をスタートしております。
(時間を決める際も、15分おきに設定した選択肢を提示し、その中から選んでもらっています)
これをおこなってから時間が来ると、自分から「◯時になったから、ママねるよー」と寝室に行くようになりました!
おまけにあんなに寝なかったのに、布団に入った瞬間スッと寝ることも。
私自身「寝かしつけ終わったら家事をしないと…」などの焦る気持ちが減ったことも、長男の安心材料になったのかもしれません。
「寝かしつけ、もう1時間以上やっているな…どうしよう…」と焦った時に、ぜひ試してみてくださいね。
②子どもと一緒に寝ちゃう
思い切って子どもと一緒に寝る、というのもママの気持ちをラクにしてくれます🌷
私は①一度リビングで過ごすとセットで行うことが多いです。
子どもを遊ばせながら、食器を洗い、保育園の用意も済ませておく。
そして「今日はこの子と一緒に寝る!」と決めたら、子どもと一緒に本を読みながら軽く晩酌もしてしまいます🍷
そうするとだんだん焦りやイライラがおさまり、「今日はもういいや〜」という気持ちに。
不思議ですよね😂
でも本当なんです。
そしてママの気持ちが落ち着いたからか、一緒に寝れるという安心感なのか、
長男の寝つきも不思議とよくなるのです◎
ぜひみなさまも、騙された!と思ってやってみてくださいね✨
効果を実感できるはずです!
最後に:発達障害児の睡眠は「質」を重視する
ここまでお読みいただきありがとうございます。
「発達障害児はなぜ寝ないのか」そして、「どうしたら寝られるのか」「寝ない時にママがラクになる方法」についてお伝えいたしました。
よく睡眠について調べると、「◯歳は1日◯時間寝ましょう」と出てくるかと思います。
それを見るたびに「うちの子は全然足りていない…」と落ち込んでしまいますよね。
確かに睡眠時間は大事かもしれません。
しかしそれ以上に「質」を重視していただきたいな、と思います💡
短い時間でも、その子がぐっすりと熟睡でき、朝機嫌良く起きてくるのなら、それがその子の睡眠パターン◎
周りの子と違くても大丈夫🙆🏻♀️
成長もします!
うちの子は睡眠時間のわりに背も高いし、記憶力も良いですよ✨
(親バカかもしれない笑)
今回ご紹介した方法をひとつでも良いので試してみて、少しずつお子さんにあった睡眠パターンを一緒に見つけていきましょうね🌷
最後までお読みいただきありがとうございました。