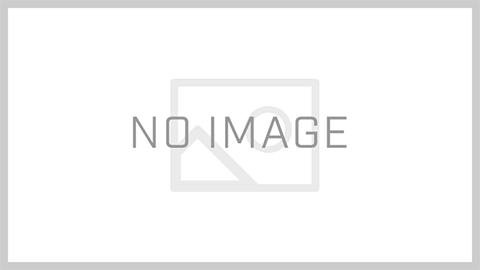タスク管理しているのに、いつも上手くいかない…
そんなふうに自分のことを責めていませんか?
こんにちは!
発達障害の長男を育てる2児のママ、さとちえです🌷
今回は「ADHDでもできるタスク管理の方法」についてお伝えします。
こちらの記事に辿り着いた方の中には、「世の中のタスク管理を色々やってみたけど、どれも上手くいかなかった…」とお悩みの方が多いのではないでしょうか?
私もそうでした。
・「タスクを書き出して細分化」しても、必ずやり忘れがある
・「優先順位をつけましょう」と言われても、そもそも優先順位が分からない
・タスクをどうしても先延ばしにしてしまう
こういった状況を長らく抱えていました。
そして、
仕事も育児も両立したいのに、タスク管理ができないから無理なんだ
と落ち込む事態に。
そんな時に知ったのが、ADHDの特性に合わせたタスク管理の方法💡
やはりADHDなど発達障害の傾向がある方は、それぞれの特性に合わせた対策が必要だったのです。
私も特性に配慮し自分なりに工夫を重ねた結果、徐々にタスク管理ができ、仕事も育児も円滑に回せるようになってきました!
今回の記事では「ADHD傾向の私が試行錯誤の末に見つけ出した、タスク管理術について」ご紹介いたします。
同じように悩む方が「この方法試してみようかな!」と前向きな気持ちになれ、一つでも多く試すことができますと嬉しいです!
ADHDでもタスク管理はできる!
 これまで多くの方が「タスク管理ができない」「だから仕事もできないんだ…」と諦めてきたのではないでしょうか?
これまで多くの方が「タスク管理ができない」「だから仕事もできないんだ…」と諦めてきたのではないでしょうか?
でもまだ諦めないでください。
ADHDの特性に合わせた対策を知れば、ADHDの傾向がある方でもタスク管理はできます!
巷に溢れているタスク管理術は、大多数に当てはまる方法を伝授しているに過ぎません。
発達障害やADHDの傾向がある方には、その「特性を補うような対策」を行わなければタスク管理はできないのです。
具体的にいうと、
✅「優先順位をつけましょう!」と言われても、ADHDは脳の構造上、優先順位づけが苦手。どのようにつけたらいいのか分からない。
→第三者に優先順位をつけてもらう必要がある💡
✅「ToDoリストを作成しましょう!」と言われても、作成して終わるのがADHD。結果、忘れてタスクや予定をすっぽかしてしまう。
→リスト作成〜スケジュール入力〜リマインド通知を一括で行う仕組みが重要💡
このように、それぞれの特性に合わせて対策を講じるのが肝◎
次章では、ADHD傾向にある私が実際に試して効果のあったタスク管理方法についてご紹介します!
ADHDの特性に合わせた対策5選
 ここからは、私が実際に試した結果「タスク管理ができるようになった!」と感じられた方法をご紹介いたします。
ここからは、私が実際に試した結果「タスク管理ができるようになった!」と感じられた方法をご紹介いたします。
「いいな」と思える方法がありましたら、ぜひ試してみてくださいね🌷
①ジャーナリングをして見える化する
②生成AIを使ってタスクを細分化&優先順位づけ
③②で洗い出したタスクを紙に書いて見えるところに貼る
④保育園のお便りはNotebook LM&Geminiでカレンダーに反映
⑤小まめにリマインド通知設定をする
一つずつ解説いたします💡
①【脳内のタスクを顕在化】ジャーナリングをして見える化する
頭の中にある「忘れているタスク」をジャーナリングによって見える化していきます。
ジャーナリング:頭に浮かんでいることをノートにひたすら書き出す作業のこと
1冊のノートと1本のペンでできる、とてもカンタンな方法💡
まずは思いついたことをひたすらノートに書いていきます。
すると不思議なことに、どんどんタスクが思い出されてくるのです!
その上、ノートに書き出すと目で見て確認できるようになるので、頭の中だけでは気づかなかったタスクにも自然と気づけるように◎
とてもカンタンに行うことができるので、ぜひ気軽に試してみてください!
②【苦手なところは生成AI】タスクの細分化&優先順位づけをしてもらう
特性上どうしてもできない作業やこれまで何度も挫折したことは、思い切って生成AIに任せてみましょう!
生成AI:文章・画像・音声・動画などの新しいコンテンツを作り出す人工知能。
人の代わりにアイデアを出したり、文章やデザインを作ってくれる優れもの💡
例えば、「ChatGPTにタスクの細分化と優先順位をつけてもらう」という方法がオススメ◎
この方法は生成AIやChatGPTに初めて触れる方でも、カンタンに行うことができます!
<タスクを細分化する場合>
①ChatGPTに、ジャーナリングで見えてきたタスクを入力する
②「このタスクを実行できるレベルまで細分化してください」という一文を付け足す
③ChatGPTが自動でタスクを細分化してくれる
<タスクの優先順位をつける場合>
①ChatGPTにタスク&タスクの期限(あれば)を入力する
②「このタスクに優先順位をつけて、スケジューリングしてください」という一文を付け足す
③ChatGPTが自動で優先順位づけ&スケジューリングしてくれる
私は生成AIに出会ってから、これまで悩んできたタスク管理やスケジュール管理、頭の中の散らかりなどをどんどん解決できるようになりました!
「これはADHD(発達障害)の相棒になるものだ!」と感動したことも。
ぜひみなさんにもこの感動を体感していただきたいです😭
ほとんどの生成AIは無料で利用できるので、ぜひ気軽に試してみてください!
(オススメはChatGPTです💡)
③【視覚優位な特性を利用】タスクを紙に書いて見えるところに貼る
生成AIにタスクを細分化&優先順位づけをしてもらったら、やるべきことを紙に書いて見えるところに貼っておきましょう。
ADHDを始めとする発達障害の特性の一つに、「視覚優位」があります。
視覚優位:耳から入ってくる情報よりも、目で見た情報の方が理解しやすい&記憶に残りやすいこと。
この特性を利用しタスクを紙に書いて貼っておくことで、「やり忘れた!」を防止することが可能に◎
また、目につくところに貼っておけば次にやるべきことがすぐにわかるので、途中で違う作業に脱線しにくくなります。
私は作業スペースの壁やPC周りに貼っております💡
家事や育児に関することは冷蔵庫に貼ることも。
みなさんがよく目にする場所を活用し、ぜひ気軽に試してみてください。
④【面倒な作業も生成AI】保育園のお便りはNotebook LM&Geminiでスケジュール化する
保育園のお便りも生成AIを活用し、予定をカレンダーに反映させましょう。
今回利用する生成AIは、Notebook LMとGeminiです。
Notebook LM:自分のノートや資料、Web上のコンテンツ等を情報整理・要約・質問ができるツール
Gemini:Googleが開発した会話型AI(チャット型の人工知能)
情報収集、文章作成、画像生成を得意としているAI。
まずはお便りをPDF化し、Notebook LMに読み込ませます。
その後「今月の予定を教えてください」と質問するとその月に予定をピックアップしてくれるので、今度はコピペしてGeminiに入力します。
その際、
「Googleカレンダーにこれらの予定を反映させてください」
「◯時と◯時にリマインド通知設定をしてください」
と入力することで自分でカレンダーに打ち込まなくても、Geminiが自動でカレンダーへ反映!
面倒な作業が簡素化される上にリマインドまで設定してくれるので、「予定をカレンダーに入れるのがめんどくさい」「予定を忘れた!」というのを防ぐことができます。
私は毎月この作業を行うようになってから、「保育園の持ち物を忘れ、家と保育園を何度も往復しながら届ける」という恥ずかしい行動を減らすことができました。笑
細かい手順は、今後別記事で紹介予定です!
ぜひそちらを読みながら手を動かしてみてください。
実際の画面付きでわかりやすく解説予定です。
家族や仕事の予定をたくさん抱える忙しいママこそ、ぜひ試してみてほしい!
きっとみなさんの良き「相棒」になってくれるはずです✨
⑤【スケジュール忘れ防止】こまめにリマインド通知をする
Googleカレンダーや携帯のリマインド機能を利用し、こまめにリマインド通知を行います。
私は予定の時間まで、5〜6回はリマインド通知を行っております。
(予定の1日前、当日の朝、予定の2時間前、1時間前、30分前、15分前)
ここまで細かくリマインド通知をしているので、「予定をうっかり忘れる…」ということがグンと減りました◎
それでも作業に集中していると忘れがちになるので、15分前に通知も欠かせません。
かなり原始的な方法ではありますが、こちらの設定もGeminiにお任せできるのでカンタンに行うことができます!
「そんなに何回も設定するのは面倒かも」と思った方こそぜひ、Geminiを活用してみてください!
カンタンなのに、うっかり忘れがグンと減って安心できますよ🌷
最後に:特性に合わせた対策でタスク管理はできる!
 いかがでしたか?
いかがでしたか?
ここまでADHDの特性に合わせたタスク管理の方法をご紹介いたしました。
これまでタスク管理ができずに悩んでいた方も「この方法試してみようかな」と前向きな気持ちになれたのではないでしょうか?
特性に合わせた対応を行えば、タスク管理は誰でもできます!
私も長らく悩んできましたが、今では「タスク管理楽しい〜!」と思えるまでになっております◎
ぜひ一つでも多く試し、その楽しさをみなさんにも実感していただきたいです!
この先も特性による生きづらさから、何度も「上手くいかないな」と思うことがあるかもしれません。
そのような時は何度でもまたこのサイトに来ていただき、乗り越えるためのヒントを得ていただけますと嬉しいです🌷
最後までお読みいただきありがとうございました。